大野 隆
専任教員紹介
大野 隆 ONO Takashi
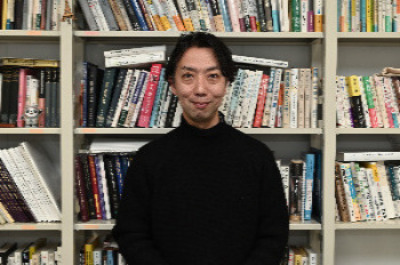
| 研究テーマ | 政治経済学(景気循環・不平等・搾取) |
|---|---|
| 研究室 | 良心館575号室 |
| 演習(ゼミ)紹介 | 経済・社会の課題を見つけ、解決する! |
| 詳細 | 研究者データベース(オリジナルサイト) |
雇用の決定権をもつ資本家(経営者)が、利潤追求のために機械を導入して、労働者の合理化を行う点に着目し、研究を進めてきました。このような視点から研究に取り掛かろうとしたのは、「なぜ失業がなくならないのか?」という素朴な疑問からでした。新聞では、新技術の開発による労働者のリストラ(合理化)の記事が目立っているさなか、一般的に言われる「労働者の賃金が高いや、景気が悪い(需要が少ない)」という説明だけでは納得できず、企業が新たに機械を導入して労働者を削減する合理化の影響を考察したいと考えるようになりました。
失業を考える場合、短期という資本ストック(機械)の変化を考慮しない期間で、通常、分析を行います。他方、資本ストック(機械)の変化を考慮する長期では、失業を想定しません。私は、資本ストック(機械)の変化を介して成長や雇用に与える中期という期間に注目し、資本ストック(機械)と雇用の関係を研究しています。具体的には、約10年という期間を念頭に、インフレ、経済停滞、金融制度、労使交渉制度が、資本ストック(機械)と労働の選択問題や企業行動を通じて、経済成長率、失業率にどのような影響をあたえるかを理論的に考察しています。
政治経済学の中の非主流派マクロ経済学(Analytical Political Economy)が専門領域です。今後は、いままでの成果をもとに、景気循環や格差の拡大といった、資本主義経済で必然的に発生する諸問題を考察し続けて行く予定です。
また、若手の後継者養成を目的としたSummer School on Analytical Political Economyに携わっています。このスクールの企画目的は、この分野に従事する、国際的にも通用する先端的研究者の育成に寄与する事です。大学院に興味ある方は是非ご参加ください。
学生へのメッセージ
経済学を専門にしていますが、基本は自分の興味の赴くままに行動しています。学生の皆さんは、大学では「よく学び・よく遊べ」を実践し、様々なことに挑戦してください。「よく学び」の面では、答えのない問に対して、問題意識(アンテナ)を持ち、先行研究をまとめ、自分自身で仮説を打ち立てる。そして、その仮説を、データや理論を用いて論理的に証明し、論文にまとめ、わかりやすく発表し興味を持ってもらう、という一連の論文作成過程を実際にやってみましょう。大学で学んだことは直接的に社会で役に立つわけではありませんが、このような学問的過程で得られる情報収集力、分析力、説明力は、卒業後の日々の生活・仕事に応用可能で、それは豊かな人生につながるはずです。
私も、研究だけではなく、日々の買い物、旅行の計画、趣味(食べ歩き、その他)にも活用しているはずですが、それがうまく活かしきれているかどうかは、また別の話。。。
演習(ゼミ)
演習テーマ:政治経済学の視点から、経済・社会を考える
「ともに学び、自分と向かい合う!」
大野ゼミでは、資本主義経済の構造やメカニズムを学び、政治経済学的視点から、労働、企業、お金、望ましい社会とは何かという本質的な問いを掘り下げます。そして、『より良い社会』のためのどうしたらいいのかを模索し、提案します。
『より良い社会』とは何かを考えることは、自分にとっての重要な価値観を明確にするプロセスを明らかにすることに繋がります。政治経済学を学び、自分と向かい合います。
大野ゼミの特徴は6つです。
#1 政治経済学を学び、本質を考える。
#2 考えるためのフレームワーク(考える力/ストーリーを作る力/伝える力など)を学ぶ。
#3 繰り返し学ぶ
#4 ゼミで学んだフレームワーク(基礎)を自己理解やビジネスに「応用」する。
#5 学びを通じて、同期・先輩・後輩・先生・立命館・OBOGとつながる。
#6 経済社会を学問的に理解し、「より良い社会」を考えることで、自分の価値観を知り、自己理解を深める。
#1 政治経済学を学ぶ
ゼミでは、政治経済学を通じて経済や社会の本質を深く掘り下げます。資本主義経済が抱える矛盾や課題(例:賃金格差や階級問題)を、理論やデータを活用して分析します。テーマは、資本家と労働者の関係、賃金、大量消費、格差、技術進歩、失業、景気循環など、現代社会の核心的なテーマです。
政治経済学を学ぶことで、当たり前と思っていた事象を疑い、日常の背後に隠れた本質を追求する力が養われます。
また、政治経済学はテーマが非常に幅広いため、何を研究したいのか決まっていない人や、将来の研究テーマに不安がある人も、自分にぴったりの研究テーマを見つけることができます。
#2 考えるためのフレームワークを学ぶ
ゼミでは、政治経済学の視点から論文を書くために、以下の、基礎的な思考のためのスキル(フレームワーク)を学びます。
*調べる
*読む
*問う
*書く
*伝える
*論証する(データ・理論)
*グループワークの進め方
これらの思考のためのスキル(フレームワーク)は、卒業後もあなたの強力な武器となります。ゼミを通じて考える力を高めることは、どんなフィールドでも確かな成果を出せる力を養います。卒業時までに確実に習得し、次のステップへと進む準備を整えましょう。
#3 繰り返し学ぶ
フレームワークを「わかる」から「できる」にするためには、繰り返すことが重要です。そこで、2年秋学期にはフレームワークを集中的に学び、様々なグループワークを通じて、難しい課題にも積極的に挑戦します。失敗を恐れず、互いにサポートし合う雰囲気の中で成長を促進します。さらに、論文を繰り返し執筆することで、2年半をかけて、思考のためのスキル(フレームワーク)を着実に身につけていきます。
2年: 3〜4人1組でインプットを重視
3年: 2〜3人1組で論文を書き、実践力を高める
4年: 卒論を1人で書き上げ、自分の力とする
#4 ゼミで学んだフレームワークを自己理解やビジネスに応用する。
ゼミで学ぶ、基礎的な思考のためのスキル(フレームワーク)を土台に、自己分析やビジネスへの応用力を養います。
政治経済学を学び、論文を書くということは、経済社会のルールを深く考察することです。この分析の視点を社会から自分自身に置き換えると、自己分析に繋がります。つまり、ゼミの学びと自己分析は本質的に同じプロセスであり、ゼミで得た思考のためのスキルを応用することで、自分をより深く理解できるようになります。
ゼミで培った「本質を追求する力」を活かすことで、ビジネスにおいても、表面的なニーズを超えて、顧客が本当に求めているものを深く理解し、的確に捉えることができるようになります。
また、ゼミでの学びを実社会でどう活用するかを考えるワークショップも開催し、理論と実践を結びつける機会を提供します。
#5 学びを通じてつながる
大野ゼミでは、学びを通じて、様々な人とつながることができます。
*1 同期とのつながり
ゼミ内の仲間、特にグループワークを通じて共に悩み、活発に議論しながら成長していく同期は、非常に大切な存在です。難しい課題にも協力して挑戦し、成功や失敗を共有することで、お互いを高め合います。共に学ぶ中で自然と絆が深まり、ワーク後には自主的にグループや個人で打ち上げを行い、さらに親睦を深めることも。
そのため、単独でゼミに入った子でも溶け込みやすい環境です。
こうした同期との関係は、大学生活の中でかけがえのない財産となるでしょう。
*2 先生との繋がり
発表やレポートには丁寧なフィードバックを行い、希望者には半年に1〜2回の面談を実施します。面談ではゼミの振り返り(他己分析)を通じて、個々の学びの意義を再認識し、モチベーションを高めます。
さらに、現状や目指すレベルに基づき、次に取り組むべき具体的な課題を適切に助言し、各個人の学びや目標に向けた成長をサポートします。
*3 先輩・後輩とのつながり
論文作成で行き詰まったときには先輩に相談できるだけでなく、後輩の指導も行います。こうした交流をきっかけに、就活のエントリーシート(ES)の添削をお願いしたり、先輩・後輩との交流を深めたりすることができます。
*4 立命館大学敦ゼミとのつながり
立命館大学経済学部の大野敦ゼミとは、半期に1〜2回の交流を行います。敦ゼミのゼミ生とは何度も顔を合わせるため、自然と親しくなり、新たなネットワークを築くことができます。また、大野敦先生から直接コメントをいただく機会があり、名前を覚えてもらえることも。
さらに、就職企画は合同開催されるため、参加できるイベントが増え、頼れる卒業生とのつながりも深まります。
*5 OBとのつながり
年に一度、OBが集まり、ゼミで行った自己分析をさらに深掘りし、自己理解を深める機会を提供します。OBは単に経験談を話すのではなく、ゼミで実践している自己分析をサポートし、社会人目線でのPR方法を提案します。
ゼミ生、先生、先輩後輩、立命館、OBOGらと、ともに学び、繋がりましょう!
#6 経済社会を学問的に理解し、「より良い社会」を考えることで、自分の価値観を知り、自己理解を深める。
ゼミでは、論文執筆を通じて現代社会の課題を明らかにし、より良い社会のあり方を探求します。資本主義の問題点や望ましい社会について深く考えることは、学びと向き合いながら自分の価値観を見つめ直す貴重な機会となります。
サークルやアルバイトを通じた自己分析とは異なり、学問的な視点から自己を探究し、新たな自分に気づくことができるのが本ゼミの大きな特徴です。
#7 本ゼミでの学びと、卒業時に得られる力
論文を書くことを繰り返し、思考のスキル(フレームワーク)を身につけ、卒業論文を書き上げたゼミ生は、以下のことができるようになります。
*人と一緒に仕事をする上で必要なコミュニケーションスキルが身につく。
*自分自身を深く理解することができるようになる。
*自分で考えたことを、相手に納得してもらうことができるようになる。
*人に伝わるプレゼンができるようになる。
*働く上で求められる「考える・分析」ができるため、卒業後、生き生きと働ける。
#8 どんな人に来てほしいか
過去のゼミ生をみていると、以下のような人たちが多い気がします。当てはまっていると思う人は、ぜひゼミ見学会や座談会に来てください。
*政治経済学の授業を面白いと思う人。
*資本主義経済の矛盾(階級、格差、南北格差、不況など)に興味関心がある人。
*自分の探究心に時間を捻出できる人
*勉強するときは、切り替えて真面目に取り組める人
*わからないからと言って、投げ出さない人
*協調性のある方
*グループで協力して何かを成し遂げたいと考えている方
| 2年次演習 |
|---|
|
政治経済学2を受講しながら、ゼミでは基礎的な思考のためのスキル(フレームワーク)を学びます。フレームワークを集中的に学び、様々なグループワークを通じて、難しい課題にも積極的に挑戦します。失敗を恐れず、互いにサポートし合う雰囲気の中で成長を促進します。 [履修条件] |
| 3年次演習 |
|---|
|
「3年次演習」では、テキストの輪読とともに、2〜3名のグループで自らの選んだテーマで論文を執筆し、論理力と分析力の向上を目指します。執筆した論文は、政治経済学学生ゼミナール大会(UCPE)で発表します。 [履修条件] |
| 卒業研究 |
|---|
|
「卒業研究」では、今まで培った論理力と分析力をもとに、独力で卒業論文を執筆します。 [履修条件] |
関連する科目
既修・併修を強く勧める科目
- 政治経済学
- 社会政策
- 現代資本主義
- 経済学の歴史
既修・併修が望ましい科目
履修を勧める2年次演習関連科目
履修を勧める3年次演習関連科目
関連する演習
| 西岡 幹雄 | 地域の潜在価値の発見と新たな経済社会インフラの展開~コロナ後の地域・都市のあり方と世界の変容~ |
|---|---|
| 小野塚 佳光 | 国際政治経済学:ガバナンスの革新と国際システムの歴史的な調整 |
| 山森 亮 | No one will be left behind:連帯経済×社会政策×SDGs |
| 横井 和彦 | 経済のグローバル化と中国経済 |
| 谷村 智輝 | グローバル資本主義の現状とそのゆくえ |
学生による「私のゼミ紹介」
Q1.大野ゼミの魅力は?
Q2.ゼミ活動を通して得たもの
- M先輩
- 論理的に考え伝えることの重要性。
物事を多面に見る力。
社会人になっても会って話したいと思える友人。
- X先輩
- 社会や身近な問題により関心深くなる。
気持ちを切らさず努力し続けることの楽しさ。
思うようにいかないときこそ、「乗り越えて見せよう」といったすぐにあきらめない姿勢。(精神面でも強くなれた気がする!!)
- O先輩
- 考え抜く忍耐力。(求められる水準が高い)
Q3.大野先生はどんな人?
- M先輩
- とても面倒見がいい方です。様々な相談に乗ってくださり「生徒との距離が近い」ことが特徴です。また、子煩悩で、よくお子さんを授業につれてこられます。
- T先輩
- 学生のことをよく見てくれている。そのため耳の痛いようなことも指摘してくださる。大学生になってから、こんな先生に出会えるのは稀だと思います。頑張れば頑張るだけFBがいただけるため、そういうのが好きな人には向いてるかも。ともちゃん大好き(笑)(先生のお子さんです♪)
Q4.ゼミの1番の思い出は?
- M先輩
- (真面目Ver)インカレの研究報告で賞をいただいたこと。
(楽しさVer)ゼミのみんなでカラオケや飲み会、夏にはユニバにも行きました♪
- M先輩
- 3回生での論文作成です。チームメンバーと、あーでもないこーでもないと議論しつづけ完成したときの達成感はとても大きいものでした。
- Y先輩
- 琵琶湖近くのリトリートセンターでの、立命館ゼミとの合同合宿。他ゼミの人とも仲良くなれる!
Q5.どういう人が向いているか
- T先輩
- ①勉強が好きな人
②必要な時に素直に頼れる人
③物事を諦めず最後までやり遂げられる人
3つどれかに当てはまれば向いてると思います!
- K先輩
- 物事の矛盾に気が付く人
- Y先輩
- ゼミに対して学びを求めている人、
もっと自分の能力を高めたいと思っている人、
経済学が嫌いじゃない人、です!
Q6.社会に出て、ゼミの学びが役立った瞬間は?
- H先輩
- 上司・取引先に対しての説明を分かりやすく行えた時。(人前に出て話す機会を多く与えてもらったから。)
- Y先輩
- 普段の業務の問題点や課題を整理するとき。(ゼミで学んだピラミッド分析を活用)
- K先輩
- 端的に物事を分かりやすく伝えるとき。
- M先輩
- 様々な手法を使って、アウトプットを出そうとしているとき。
ゼミ生からの一言!
大野ゼミでは、自分の興味のあることをとことん研究したい人、今の環境に満足していない人、学生生活のうちで胸をはってやりきった!と言える経験が欲しい人、ゼミ活動を通じて自分を成長させたい人など、少しでも大野ゼミに興味を持った方はぜひ説明会やゼミ見学に足を運んでみて下さい!個性豊かなゼミ生一同お待ちしています!
②論理的思考力・文章力・批判的に物事を見る力
③生徒のことをよく見て指導してくださる先生の存在